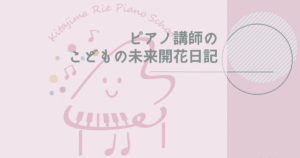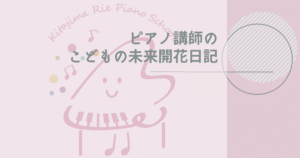前回は「感性が光ると、どんな未来がひらけるのか」についてお話しました。
今日は、少し切り口を変えて「感性が学力や思考力につながる理由」を考えてみたいと思います。
目次
感性と学びの関係とは?
「学力」というと、文字や数字を正しく理解することを思い浮かべる方が多いかもしれません。
でも実は、その前に必要なのが “感じとる力=感性” です。
たとえば──
- 絵本の物語に共感できるから、言葉を覚えやすい
- 数字の並びを「リズム」として感じられるから、数が楽しくなる
- 「どうして?」と感じるから、調べたい気持ちが育つ
こうした「学びたい!」という気持ちは、すべて感性から芽生えていきます。
感じることが「考える力」の出発点
思考力は、突然生まれるものではありません。
まず「気づく」→「感じる」→「考える」という流れがあります。
たとえば、夕焼けを見て「きれい」と感じること。
そこから「どうして赤いんだろう?」という疑問が生まれ、さらに「光の仕組み」や「科学」に興味が広がっていきます。
つまり、感性は思考のスイッチを押す役割をしているのです。
ピアノレッスンで育つ感性と思考
ピアノのレッスンでは、たくさんの「感じる→考える」の流れがあります。
- 音を聴いて「優しい音だな」と感じる
- 「どうしたら優しく弾けるかな?」と考える
- 実際に弾いて、また違いを感じる
この繰り返しが、自然と思考力を鍛えてくれるのです。
「ただ弾く」だけではなく、**“音を感じて工夫する”**というプロセスこそが、感性と思考を結びつける大切な瞬間です。
学びを楽しくする感性の力
勉強でもピアノでも、「やらなきゃ」では長続きしません。
でも「おもしろい!」「なんだろう?」という気持ちがあると、子どもは夢中で学びます。
感性が育っている子は、
- 興味を見つけやすい
- 疑問を持ちやすい
- 試すことを楽しめる
だからこそ、自然と学力や思考力も伸びていきます。
まとめ
- 感性は「学びたい!」という気持ちを生む力
- 感じることが、考える力の出発点になる
- ピアノレッスンは「感じる→考える」の流れを自然に経験できる場
感性を育むことは、決して音楽だけに役立つわけではありません。
これからの時代を生きる子どもたちにとって、「感じて、考えて、学ぶ」力の土台になるのです。
だから私は、ピアノの音を通して「感性の芽」を大切に育てたいと思っています。