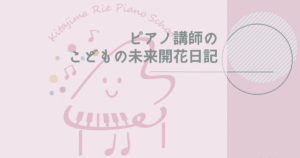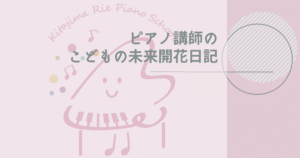前回は、感性が創造力や表現力を育てることについてお話しました。
今回はさらに一歩進めて、感性と共感力の関係について考えてみたいと思います。
目次
共感力ってどんな力?
共感力とは、「相手の気持ちを感じ取り、理解する力」のことです。
幼児期から小学校低学年にかけて、この力の土台がつくられると言われています。
- 「友達が悲しそうにしているのに気づく」
- 「お母さんの疲れた表情に気づき、そっと声をかける」
- 「曲を聴いて、作曲者の気持ちを想像して表現する」
こうした小さな体験の積み重ねが、共感力を育てます。
感性が共感力を支える
感性とは、目に見えないものを感じ取る力。
その感性を育むと、自然と相手の気持ちや場の空気にも敏感になります。
ピアノのレッスンでは、次のような経験が共感力につながります。
- 音楽の表情を感じ取る → 曲に込められた感情を理解
- 友達や先生の演奏を聴く → 相手の思いを受け取る体験
- 自分の表現を聴いてもらう → 相手の反応を感じる
「自分の心で感じる」ことが、相手の心を感じる力の基礎になるのです。
レッスンでの具体的な取り組み
私の教室では、次のような活動を通して共感力を育てています。
- 聴き合いワーク → お互いの演奏を聴き、感じたことを言葉にする
- 感情カードで表現 → 喜び・悲しみ・楽しさを音に乗せる練習
- 即興演奏のやり取り → 相手の音に応じて、自分も演奏で返す
これらを通じて、子どもたちは自分の気持ちを表現しながら、相手の気持ちを感じ取る体験を積んでいきます。
共感力は人との関わりに生きる
共感力は、ただ音楽が上手になるためだけでなく、友達や家族との関係、将来の社会生活でも大きな力になります。
「相手の気持ちを想像できる」
「自分の思いを伝えられる」
そんな経験は、子どもたちの心を豊かにし、安心して挑戦できる環境をつくります。
まとめ
- 感性を育むと、共感力の土台が作られる
- ピアノを通して、相手の気持ちや音楽の感情を感じ取る体験ができる
- 自分の心で感じることと、相手の心を感じることはつながっている
- 共感力のある子どもは、人との関わりも、学びも、より豊かになる
ピアノは、音楽を楽しむだけでなく、感性と共感力を育む場所でもあります。
これからも、子どもたちが安心して自分の気持ちを表現し、相手の気持ちを感じ取れる心も育つレッスンを大切にしていきたいと思います。