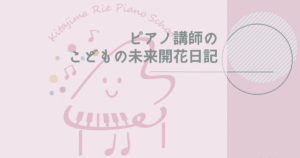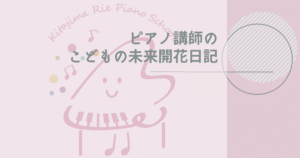前回は、感性と共感力の関係についてお話しました。
今回は、感性が集中力とどのようにつながるのか、ピアノレッスンを通して見ていきたいと思います。
目次
集中力ってどんな力?
集中力とは、やるべきことに注意を向け、一定時間取り組み続けられる力のことです。
幼児期から小学校低学年にかけて、遊びや学びの中で少しずつ育っていきます。
しかし、ただ「長く座って弾く」だけでは集中力は育ちません。
必要なのは、心が「これに向かいたい!」と思える瞬間を増やすことです。
感性が集中力を支える
感性とは、目に見えないものを感じ取る力。
この力が育つと、子どもは自然と「音や表現に耳を傾ける」ようになります。
ピアノのレッスンでは、次のような体験が集中力につながります。
- 音の変化やリズムの違いを感じ取る
- 曲の雰囲気や色を想像する
- 自分の表現を考え、音で試す
「聴く」「感じる」「考える」の繰り返しが、無理なく注意力を伸ばします。
レッスンでの具体的な取り組み
私の教室では、次のような活動で感性と集中力を育てています。
- 音のイメージ遊び → 「この音は風みたいに」「雨みたいに」
- 即興演奏チャレンジ → ルールは一つだけ決めて自由に表現
- 色や物語との連動 → 音を色やストーリーに置き換える
短時間でも「夢中になれる」瞬間を積み重ねることで、集中力が自然に育っていきます。
集中力は日常にも生きる
集中力は、勉強や遊びだけでなく、生活全般で役立つ力です。
自分の思いを丁寧に聴き、音や表現に向かう体験は、心を落ち着ける習慣にもつながります。
小さな子どもでも、音楽の中で「集中している時間」は、安心感と満足感を伴う大切な時間。
これが積み重なることで、学びに向かう力や挑戦する力も自然と伸びていきます。
まとめ
- 感性を育てることで、自然に集中力の土台ができる
- 音楽を「感じる・考える・表現する」ことで集中する力が育つ
- 集中力は、学びや日常生活での挑戦にもつながる
- ピアノレッスンは、楽しみながら集中力を育てる場所
ピアノは、単に音を弾く場所ではなく、心を整え、集中する力を育む時間でもあります。
これからも、子どもたちが感性を感じながら、自分らしく集中できるレッスンを大切にしていきたいと思います。