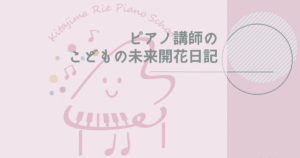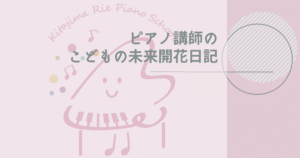― 五感で音を学ぶから、音楽が“自分のもの”になる ―
① 「感じて学ぶ」って、どういうこと?
モンテッソーリ教育の根っこには、
「頭で覚えるより、体で感じる」という考え方があります。
たとえば子どもが“長い”と“短い”を学ぶとき、
教科書ではなく、実際の棒を手で持ち、目で見て比べます。
「同じじゃない」「こっちが長い」と、感覚を通して理解する。
ピアノもまったく同じです。
「ドはここだよ」と教わるよりも、
音を聴いて、「これがドの感じだ」と心と体で覚えていく。
その瞬間、知識が“体験”に変わるのです。
② 指先・耳・目・心──すべてを使って学ぶ
モンテッソーリ式プレピアノでは、
鍵盤だけでなく、さまざまな感覚教具を使います。
・音の高さを比べるカード
・強弱を感じるリズム棒
・音の印象を色で表す「おとのたね」ワーク
・紐通しやリボン結びなど、指先の感覚を育てる活動
これらは、どれもピアノに直結しています。
指先の感覚が鋭くなることで、
鍵盤を「押す」から「感じて鳴らす」へと変わっていきます。
③ 感覚を使うと、集中が“深く”なる
モンテッソーリ教育の子どもたちは、
小さな活動に夢中になる時間を大切にしています。
感覚を使う活動は、
脳の「集中ネットワーク」を安定させる働きがあると
脳科学でもわかっています。
ピアノでも、
「耳で聴き、目で見て、指で感じる」活動があることで、
自然と深い集中の流れに入っていきます。
「気づいたら10分も同じことしてた!」
そんな瞬間こそ、子どもが最も成長している時間です。
④ 「わかる」より、「わかった気がする」を大切に
モンテッソーリのレッスンでは、
先生が「正解を教える」ことはほとんどありません。
たとえば、
「この音は高いね?」「この音は低いね?」ではなく、
「どう聴こえた?」と問いかける。
子どもが感じ取った感覚そのものが、
その子にとっての“答え”になるからです。
ピアノも同じで、
「音を当てる」よりも、「音を感じ取る」。
その繰り返しが、やがて確かな“音感”へと育っていきます。
⑤ 感覚で学ぶと、音楽が自分の言葉になる
感覚的に学ぶことで、
子どもたちは「音」を“知識”ではなく“感情”として受け取ります。
「この音、きらきらしてる」
「この曲、夜みたい」
そんな風に、音が“ことば”になる瞬間があります。
それは、音楽をただ弾くのではなく、
音で自分を表現できるようになる第一歩。
感覚を使って音を学ぶことは、
ピアノを通して「心で感じる力」を育てることなのです。
モンテッソーリ式ピアノレッスンでは、
「感じてわかる」「触って覚える」「心でつかむ」ことを大切にしています。
音楽の基礎とは、
五線譜や理論の前にある“感じる体験”の積み重ね。
この感覚があるからこそ、
どんな曲にも心を込めて弾けるピアニストへと育っていきます。