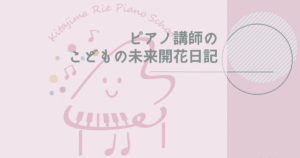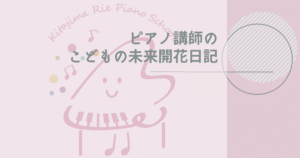前回の記事では、ピアノが「正解のない学び」であることをお話しました。
今日はそこから一歩広げて、今注目されている STEAM教育 とピアノ教育の共通点について考えてみたいと思います。
目次
STEAM教育とは?
STEAMとは、
- Science(科学)
- Technology(技術)
- Engineering(工学)
- Art(芸術)
- Mathematics(数学)
の頭文字を合わせた教育の考え方です。
「理系と文系を分けない」「知識を暗記するのではなく、実際に使って考える力を育てる」ことが大きな特徴です。
つまり、ひとつの正解を探すのではなく、自分なりの答えを作り出す学び。
ピアノも「正解を一つにしない学び」
実はこの考え方、音楽教育にとても似ています。
ピアノのレッスンでは、同じ曲を弾いても子どもによって表現が違います。
その違いは「間違い」ではなく、それぞれの感じ方や考え方の現れです。
たとえば、
- ドビュッシーの曲を「夜の星空みたい」と感じる子
- 同じ曲を「水のきらめきみたい」と表現する子
どちらも素敵で、どちらも正解。
音楽の中で「自分だけの答えを見つける体験」ができるのです。
STEAM教育と音楽教育の重なり
STEAM教育も同じです。
科学の知識を使ってものを作るとき、正解は一つではありません。
数学の問題解決にも、いくつかの方法があります。
そして「A(Art=芸術)」が入っていることが示すように、創造力や表現力があってこそ、科学や技術も生きてきます。
ピアノ教育で育つ「表現力」や「自由に考える力」は、まさにSTEAMの土台になるものです。
子どもたちに届けたい力
これからの時代を生きる子どもたちには、
- 与えられた問題に正解を出す力
- 自分で課題を見つけ、考え、形にする力
の両方が必要です。
ピアノはその後者、「自分で答えを生み出す力」 を、日々の音楽体験の中で自然に育てていきます。
まとめ
STEAM教育が目指すのは「正解を探す」だけでなく「答えをつくる、みちびく」学び。
そしてピアノもまた、子どもたちが自分の感じ方を音にし、表現することで、正解のない学びを楽しむ場です。
だから私は、ピアノを通して育まれる力が、未来を生きる子どもたちの大きな財産になると信じています。