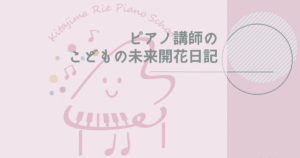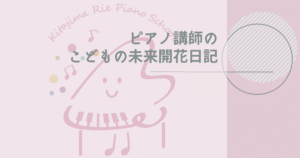前回は、感性が集中力にどうつながるかをお話しました。
今回は、感性が伸びることで、子どもたちの表現力がどのように育つのかをご紹介します。
目次
表現力って何だろう?
表現力とは、自分の思いや気持ちを、言葉や動き、音で相手に伝える力です。
ピアノにおいては、ただ音符通りに弾くのではなく、**「こんな気持ちで弾きたい」**を音で伝える力を指します。
小さな子どもでも、音やリズムを感じて表現する楽しさを経験することで、自然と自分の思いを音にのせられるようになります。
感性が表現力の土台になる
感性とは、目に見えないものを感じ取る力。
この力が育つと、子どもは**「音の色」や「リズムのイメージ」を感じ取り、自分なりの演奏に変換**できるようになります。
例えば、同じ「ド」の音でも、明るく軽やかに弾く子もいれば、ゆったりと落ち着いた響きにする子もいます。
どちらも正解であり、感じたままを表現することが大切です。
レッスンでの具体的な取り組み
私の教室では、表現力を育てるために次のような活動を取り入れています。
- 即興演奏 → ルールは一つだけ、自由に音を選んで演奏
- 音と物語を結びつける → 音を聞いて「雨」「風」「森」などを想像
- 感情を色で表す → 曲の気持ちを色や形で表現
こうした活動を通して、子どもたちは自分の感覚を信じて表現する経験を積み重ねていきます。
表現力は日常でも活きる
表現力はピアノだけでなく、日常生活でも大きな力になります。
自分の思いを言葉や行動で伝えられる子は、人との関わりもスムーズになり、思いやりや共感力も自然と育ちます。
ピアノを通して「感じる・考える・表現する」体験は、子どもたちの心を豊かにし、自己肯定感も支えてくれるのです。
まとめ
- 感性が育つと、音やリズムに自分の思いをのせられる
- 表現力は「正解がない」からこそ、自分らしさを育む
- 即興や物語との結びつきで、表現力の幅が広がる
- 音楽を通した表現体験は、日常生活のコミュニケーション力にもつながる
ピアノは、自分の心を音で伝える喜びを学ぶ場所。
これからも、子どもたちが感性を感じながら、自分らしく表現できるレッスンを大切にしていきたいと思います。