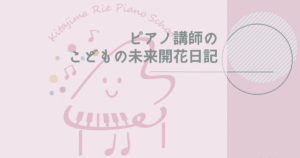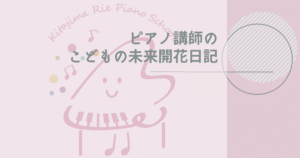前回は、感性が表現力を育むお話をしました。
今回は、感性が育つことで、子どもたちの学びや生活全般での力にもつながることを考えてみます。
目次
感性は「学びのセンサー」
感性とは、目に見えないものを感じ取る力。
この力が育つと、子どもは**「音や言葉の違い」「場の空気」「人の気持ち」**など、普段は気づきにくいものにも目を向けられるようになります。
たとえば、ピアノのレッスンで音の高低や強弱を感じ取る経験は、学習での注意力や観察力にもつながります。
音やリズムの変化に気づく力は、読書や算数の文章題、自然観察など、あらゆる学びの基礎になります。
日常生活でも役立つ「感じる力」
感性が育った子は、学校や家庭でも柔軟に物事を感じ取ることができます。
- 友達が困っている時に気づき、声をかけられる
- 物の扱いや言葉遣いに丁寧さが出る
- 自分の気持ちを整理して、相手に伝えられる
このように、ピアノで育った感性は、生活の中での思いやりや判断力にも影響します。
ピアノを通した感性教育の実例
曲を弾く前に「音やリズムからどんなイメージを感じるか」を一緒に考えることがあります。
- 音の強弱で「雨のしずく」や「風の動き」を表現
- 曲の気持ちを色や形で表現
- 即興演奏で自分の思いを音にする
こうした活動を通して、子どもは自分の感覚を信じる力と、周りを感じ取る力を同時に育てています。
感性は一生の宝物
今は情報があふれ、正解がひとつではない時代。
だからこそ、**「感じる力」=「自分なりの答えを見つける力」**が大切です。
感性が育った子どもは、自分の人生を自分でデザインできるようになります。
誰かのまねではなく、自分の“好き”を軸に歩むことができるのです。
まとめ
- 感性は学びや生活全般の基礎力になる
- ピアノで音やリズムを感じる経験が、観察力や判断力、思いやりにつながる
- 感性を通して、自分の人生を自分でデザインできる力が育つ
ピアノは、感性を育み、学びと生活に生きる力を伸ばす習い事。
これからも、子どもたちが音を通して感じ、考え、表現し、日常でもその力を発揮できるようなレッスンを大切にしていきたいと思います。