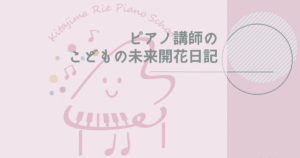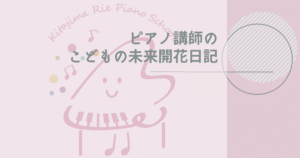これまで数回にわたり、「感性が育つこと」についてお話してきました。
シリーズを通して伝えたいことは、感性は音楽だけでなく、学びや生活全般で生きる力になるということです。
目次
感性とは何か
感性とは、目に見えないものを感じ取る力。
- 誰かの気持ちを察する
- 音や色、リズムからイメージを膨らませる
- 自分の「好き」「嫌い」に気づく
こうした力は、幼児期から小学校低学年のうちに育てると、心の安定や自己肯定感、創造力につながります。
ピアノが感性を育む理由
ピアノのレッスンでは、ただ楽譜を読むだけではなく、「音を感じ、表現する」ことを大切にしています。
- 音の高低や強弱から情景を想像する
- 色や形、リズムで気持ちを表す
- 即興で自由に表現する
こうした体験を通して、子どもたちは自分の感覚を信じ、自己表現の喜びを感じることができます。
感性は学びや生活にも生きる
感性を育てることで、学校や家庭での力も伸びます。
- 観察力や注意力が育つ
- 他者への思いやりや柔軟な判断力が身につく
- 自分の考えを言葉や行動で表現できる
ピアノで培った感性は、人生のさまざまな場面でのセンサーとして働きます。
「好き」と「楽しい」を軸に
感性を育むレッスンの大切なポイントは、正解よりも楽しさと自分らしさです。
「うまく弾くこと」だけをゴールにするのではなく、
- どう感じたか
- どう表現したいか
を大事にすることで、子どもは自ら学び、挑戦する力を育みます。
まとめ
- 感性は、自己肯定感・創造力・観察力を支える基礎
- ピアノは、音を通して感性を育てる最適な習い事
- 感性を育てることで、学びや生活、人生全体で生きる力につながる
ピアノの時間は、単なる「楽器の練習」ではなく、子どもたちの心と感覚を豊かにする時間。
これからも、音と遊び、表現の中で感性を育て、未来の力につなげるレッスンを大切にしていきたいと思います。