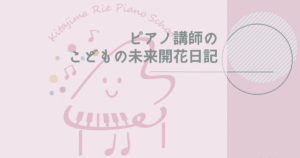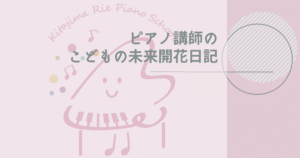〜内発的動機づけのひみつ〜
「やりたい!」は、魔法のように生まれない
子どもの「やりたい!」は、突然ひらめくように見えて、
実はその前にたくさんの“土台”があります。
安心して失敗できる環境、
認めてもらえた経験、
「自分にもできるかも」という小さな自信。
その積み重ねが、ある瞬間にふっと芽吹くのです。
だから「やりたい!」は偶然ではなく、
ちゃんと育てられる力なのです。
“外からのごほうび”では続かない
シールを貼る、褒められる、ごほうびがもらえる。
それで最初はがんばれるけれど、
やがて「もらえないなら、やらない」に変わってしまうこともあります。
それは“外発的動機づけ”と呼ばれるもの。
外の刺激がなくなると、やる気も薄れてしまうのです。
一方、“内発的動機づけ”は、
「やってみたい」「楽しい」「できた!」という内側からのエネルギー。
この“内なるやる気”が育つと、
子どもは自分で続けられるようになります。
内発的動機は「達成」より「発見」から生まれる
「うまくできた」よりも、
「気づいた」「できそう!」の瞬間にこそ、子どもは夢中になります。
ピアノのレッスンでも、
「音がつながった!」「メロディーがきれいに聴こえた!」
そんな小さな発見を見つけたとき、
子どもの瞳がいちばん輝きます。
“結果”を褒めるより、“気づき”を喜ぶ。
それが、やる気の火を消さないコツです。
「できた!」の喜びを、自分の中で味わう
やる気が続く子は、誰かに褒められなくても満たされています。
それは、自分の中で「できた!」を味わうことができるから。
レッスンでは、「先生、できたよ!」と報告してくれる生徒さんも多いですが、
本当の喜びはその前──
できた瞬間に、ぱっと顔がほころぶあの表情にあります。
“自分で自分を褒められる力”。
それこそが、内発的動機づけのいちばん強い原動力です。
“やりたい”が続く子に育つ、レッスンの仕組み
私の教室では、「上手になる」よりも「自分で発見する」ことを重視しています。
どうしてそう聴こえるんだろう?
この音、どんな気持ちかな?
この曲の中で、どんな色を感じる?
問いかけを通して、子ども自身が“自分の感性”で気づく瞬間を増やします。
その積み重ねが、内側からの“やりたい”を支え続ける力になります。
ピアノを通して育つのは、音の技術だけではありません。
自分で考え、感じ、選ぶ力──
それが「一生つづくやる気」を支える根っこになります。
まとめ
“やりたい”が続く理由は、外から与える刺激ではなく、
子どもの心の中で芽生える小さな「発見」と「自己承認」。
安心・発見・自己肯定の3つのサイクルを大切に、
これからもレッスンの中で“内なるやる気”を育てていきます。