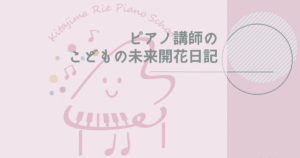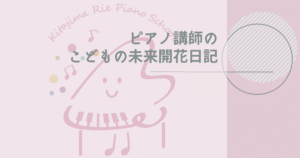〜ピアノを通して育つ“感じる力”が、子どもたちの可能性を広げる〜
感性が光る子は、“人生のセンサー”を持つ
前回は「感性とは目に見えないものを感じとる力」だとお話しました。
では、感性が光る子どもは、日常でどんな力を発揮するのでしょうか?
感性は、子どもにとって“こころのセンサー”。
「なんだかイヤ」「これ好き!」といった自分の感情をキャッチできるだけでなく、
「お友だちが困っている」「お母さんが嬉しそう」といった他者の心も感じ取ることができます。
この“センサー”があると、子どもは自分の気持ちに素直に行動でき、
他人に対しても思いやりのある判断ができるようになります。
ピアノで育つ感性の時間
ピアノレッスンは、「音を正しく弾くこと」だけが目的ではありません。
私の教室では、まず「感じること」を大切にしています。
- 音を聴いて色や情景を想像する
- 音に合わせて体を動かす
- リズムや強弱で気持ちを表現する
- 音から物語やキャラクターを思い描く
こうして、子どもたちは“心で聴く力”“感じる力”を自然に育みます。
音楽は正解がないので、思い通りに表現する楽しさを体験できるのです。
感性は自己表現のはじまり
音楽を通して「感じる」体験を重ねると、
子どもたちは自分の思いを音で表現できるようになります。
「こんな気持ちを表したい」
「こんな色に聴こえるように弾きたい」
そんな表現力が芽生える瞬間は、自己肯定感にもつながります。
「自分の感じたままでいいんだ」と思える体験が、
子どもたちの心を安心で満たしてくれるのです。
感性が育つと、未来の選択肢も広がる
情報があふれる今の時代、答えがひとつでないことも多いですよね。
だからこそ、自分の感じたことを軸に考えられる力はとても大切です。
感性が光る子は、
「私はこう感じたからこうしてみよう」
「自分の好きや心地よさを大切にしよう」
と、自分の人生の選択を自分で決める力を持ちます。
ピアノで育った感性は、学校や友だち関係、将来の夢に向かう力にもつながるのです。
今日のまとめ
- 感性とは「目に見えないものを感じとる力」
- 感性が光る子は、自分も他人も感じ取れる“人生のセンサー”を持つ
- ピアノを通して「感じる・表現する体験」が、自己肯定感や表現力につながる
- 感性は、子どもが未来を自分らしく選ぶための大切な力